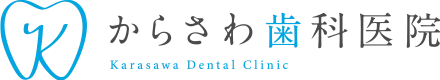こんにちは、新潟市中央区の「からさわ歯科医院」院長の唐澤です。
「親知らずってやっぱり抜いたほうがいいのかな?」と悩まれる方は多いですよね。
じつは、親知らずには「抜いたほうがいいケース」と「そのまま残せるケース」の両方があります。
今日は、その判断基準や、抜歯を考える際の注意点などをわかりやすくお話ししていきます!
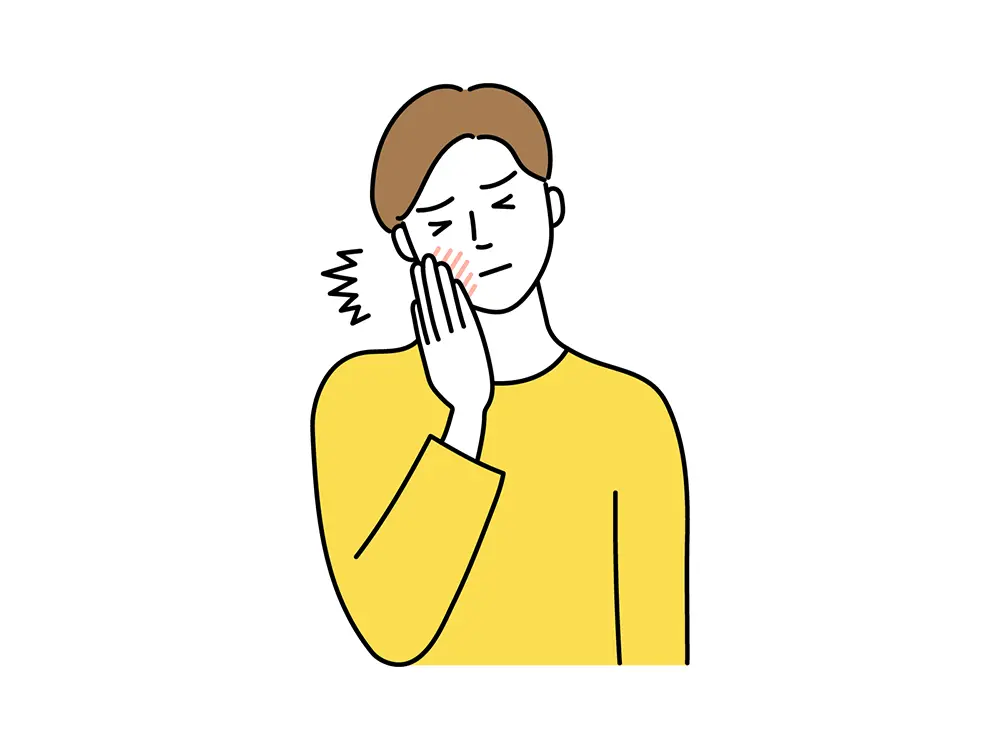
親知らずとは?
親知らずは、一番奥(8番目)に生えてくる歯のことです。
10代後半から20代前半にかけて生えてくることが多いですが、個人差が大きく、まったく生えてこない人もいれば、途中で止まってしまう人もいます。
昔は「親が気づかないうちに生えてくる歯」だから、親知らずという名前が付いたとも言われています。
抜くべき親知らず「4つのポイント」
1. 横や斜めに埋まっている
歯ぐきや骨の中で真横や斜めに生えている親知らずは、隣の歯を圧迫してしまったり、歯並びに悪影響を与えたりするリスクが高いです。レントゲンやCT撮影で歯の向きを確認し、抜歯が必要かどうかを見極めます。
2. 繰り返し痛みや腫れが起こる
親知らずの周囲が炎症を起こす「智歯周囲炎」は、痛みや腫れ、口が開けにくくなるといった症状が出やすいトラブル。特に、一部しか歯ぐきから出ていない親知らずは汚れが溜まりやすく、同じような症状を繰り返す場合は、抜歯を検討するほうが良いことが多いです。
3. 虫歯や歯周病のリスクが高い
中途半端に生えている親知らずは、ブラッシングが届きにくい分、虫歯や歯周病を発症しやすい場所。さらに、隣の歯(7番目)との間に汚れがたまって、お互いに悪影響を及ぼすケースもあります。治療が難しい位置にある大きな虫歯は、抜いたほうが負担が少ないことが多いです。
4. 矯正治療や補綴治療の邪魔になる
歯並びを整える矯正治療や、ブリッジ・入れ歯などの補綴治療の計画において、親知らずが邪魔をする場合があります。歯科医師の判断で、抜歯したほうがスムーズに治療が進むときは、先に親知らずを抜くことが一般的です。
残してもいい親知らずとは?
1. 正しい位置にまっすぐ生えている
周囲の歯に悪影響を与えず、しっかり噛み合わせに参加している親知らずは、大切な「臼歯」として機能します。噛み合わせを支えてくれる立派な歯なので、わざわざ抜く必要はありません。
2. 虫歯や歯ぐきの炎症がない
親知らずがきちんと歯ぐきから出ていて、ブラッシングがしやすい状態であれば、虫歯や歯周病のリスクも抑えられます。定期的な検診で問題が見つからなければ、そのまま残す選択肢も十分あります。
3. 将来のブリッジの支台歯として使える
もし別の歯を失ってしまったとき、親知らずをブリッジの支台歯に活用する場合もあります。今は必要なくても、将来的に役立つこともあるため、安易に抜かずに残しておくという判断も一つの方法です。
親知らずを抜くときの流れ・注意点
1.事前検査(レントゲン・CT)
・歯の位置や神経の走行をしっかり把握し、安全に抜歯できる方法を検討します。
2.抜歯の方法
・生えている角度によっては、歯ぐきを切開したり歯を分割して取り出すこともあります。
3.術後のケア
・腫れや痛みを抑えるために処方された薬を正しく服用し、激しい運動や飲酒は控えましょう。
・2〜3日ほど腫れる場合がありますが、長引く症状や強い痛みが出たら早めにご連絡を。
よくある質問
Q1. 抜歯は痛くないですか?
A. 麻酔をしっかり行うので、施術中の痛みはほとんど感じない方が多いです。どうしても不安な方は、遠慮なくご相談くださいね。
Q2. 全部の親知らずを一度に抜くべきですか?
A. 必要に応じて、タイミングをずらして抜くこともあります。生活スタイルや仕事の状況などを考慮して計画を立てます。
Q3. まったく症状がないのに抜いたほうがいいと言われました…
A. 将来的なリスク(矯正治療や隣の歯への影響)を考えて、抜歯をおすすめするケースも。納得がいかない場合は、セカンドオピニオンを求めるのも一つの方法です。
親知らずの扱いはケースバイケース
・抜くべき親知らず
横や斜めに埋まっていてトラブルが起こりがち、虫歯のリスクが高い、矯正や補綴の邪魔になっている場合
・残してもいい親知らず
まっすぐ機能しており、口腔衛生管理がしやすく、将来の支台歯としても期待できる場合
結局のところ、親知らずを抜くかどうかは個人差が大きいんです。気になる方は、ぜひ歯科医院でレントゲンやCTを撮り、歯科医師と相談して最適な選択をしましょう。からさわ歯科医院では、親知らずの抜歯からメンテナンスまで、安心のサポート体制を整えています。
「この親知らず、どうしよう…」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。
あなたのお口に合わせた最善の方法を一緒に考えていきましょう!